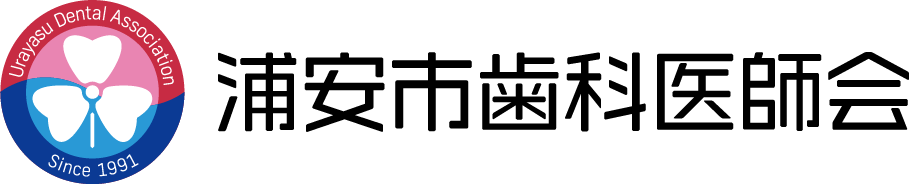歯周病が脳梗塞・肺炎・糖尿病のリスクを引き上げるメカニズム

新型コロナウイルス等様々な感染症が蔓延するようになり、口腔ケアへの関心が高まっています。細菌やウイルスによる感染症というのは、口腔を介して感染が広がるケースが多いからです。
そこで改めて注意しておきたいのが「歯周病」です。
歯周病菌は口腔内で繁殖すると、「その他の器官や臓器にまで移行」して、さまざまな病気のリスクを引き上げます。今回はそんな歯周病と全身疾患との関連についてかんたんにご説明します。
脳梗塞や心筋梗塞を誘発する

口腔内で繁殖した歯周病菌は、歯茎の血管などに入り込んで全身へと巡ります。
その際、「血管内では炎症性物質がたくさん産生」されて、血管を硬くする動脈硬化、血管を詰まらせる脳梗塞・心筋梗塞などのリスクを上昇させるのです。
歯周病によって糖尿病のリスクが上昇するのは、炎症性物質がインスリンの効果を邪魔してしまうからです。
誤嚥性肺炎との関連は?

歯周病との関連でもう一つ注意しなければならない病気に「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」というものがあります。
これはお口の中で繁殖した歯周病菌を唾液や食物と一緒に気管へと飲み込むことで発症する病気です。
若い人はそもそも誤嚥する機会がそれほど多くありませんが、「飲み込む機能が衰えているご高齢の方は十分な注意が必要」です。
実際、誤嚥性肺炎によってなくなられる方は毎年たくさんいらっしゃいます。
お口を清潔に保てば予防可能

これらの病気は、お口の中を清潔に保ち、歯周病菌が繁殖しないように努めていれば予防できます。
ですから、歯周病にかかっている人はもちろん、その自覚がない方も日頃から口腔ケアを徹底するようにしてください。
「定期検診を受ける」ことで、口腔衛生状態は良好に保ちやすくなりますよ。
まとめ
このように、歯周病は脳梗塞や心筋梗塞、誤嚥性肺炎といった病気のリスクを引き上げることがありますのでご注意ください。
歯茎が赤く腫れたり、口臭が強くなったりするなど、少しでも歯周病が疑われる症状が出たら、かかりつけの歯科医院にご相談ください。